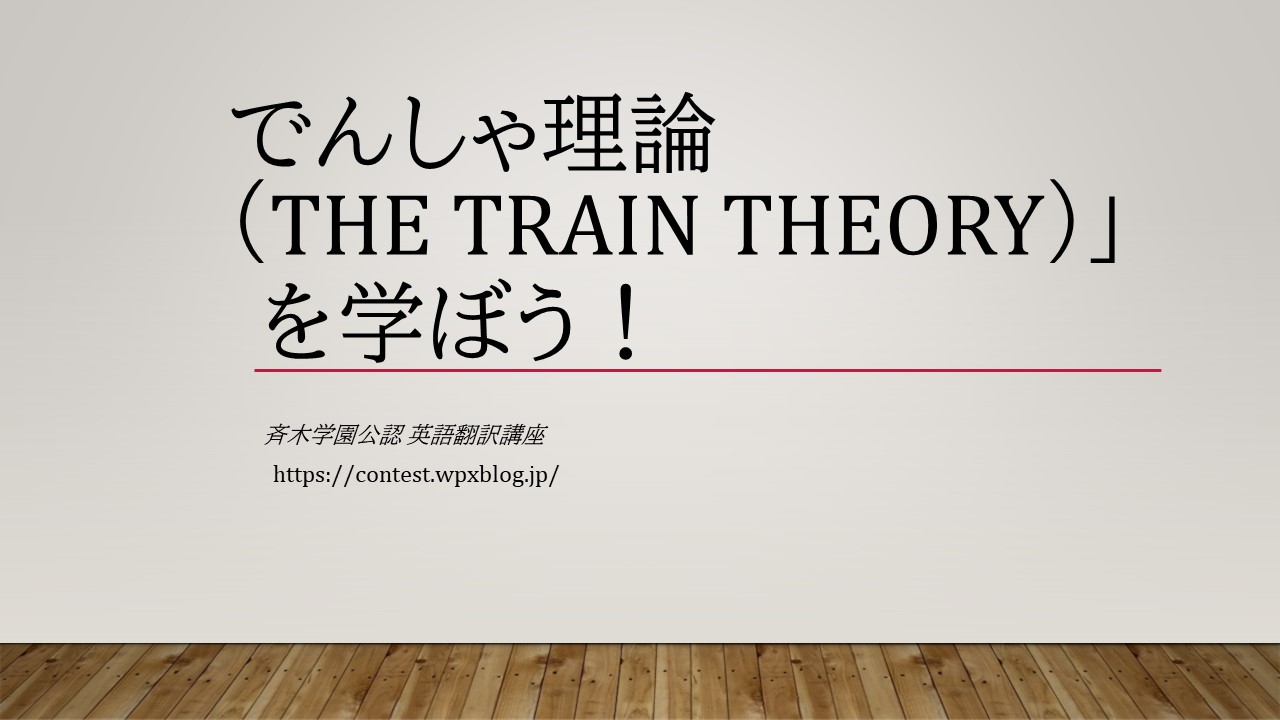「課題文」
Defense Secretary Lloyd Austin was expected to detail the figure at the last meeting of the US-led Ukraine Defense Contact Group at Ramstein Air Base in Germany.
The last package comes as the White House prepares to announce another round of sanctions on Russia, expected at the end of this week. US officials have argued they are trying to give Ukraine the greatest leverage possible ahead of possible negotiations to end the war this year. There had been an expectation the White House could impose more sanctions on Russia before the looming inauguration and amid persistent Ukrainian pressure.
The security aid announced Thursday under the Presidential Drawdown Authority (PDA) has an estimated value of $500 million and includes missiles for air defense, air-to-ground munitions and equipment for Ukraine’s use of F-16 fighter jets.
音声解説講座はこちらです
「訳例」
ロイド・オースティン国防長官は、ドイツのラムシュタイン空軍基地で開催される米国主導のウクライナ防衛コンタクトグループの最後の会合で、ウクライナ支援を具体的な数字で示すものとみられている。
この最後の支援パッケージは、ホワイトハウスが今週末に予想されるロシアに対する追加制裁を発表する取り組みの中で浮上したものだ。米国の政府高官は、今年戦争を終結させるために開催されると思われる交渉を前に、ウクライナに対して最大限のテコ入れを図ることを述べている。ホワイトハウスは、迫りくるトランプの大統領就任式を前にして、またウクライナからの絶えざる圧力を受ける中にあって、ロシアに対し更なる制裁を課すのではないかと前々から予想されていた。
緊急時大統領在庫引き出し権限(PⅮA)に基づいて、木曜日に発表されたウクライナ支援は、推定5億ドルで、それには防空ミサイルやウクライナがF-16ジェット戦闘機を使用するための空対地用の弾薬と装備品が含まれている。
———————————————–
一、分析①(概説)
今回の解説は、
第1段落の ‘Lloyd Austin was expected to detail the figure ~’
第2段落の ‘US officials have argued they are trying to ~’
‘There had been an expectation the White House could impose ~’
解説のポイントは、「動詞の語形変化への時制の働きとその訳出」です。
前半の解説では、この課題における「動詞の語形変化への時制の働きとその訳出」について、構造的視点から取り上げ、そして後半の解説では、その訳出法について取り上げます。
□ Lloyd Austin was expected to detail the figure ~
構造式:Lloyd Austin was expected to-inf (過去時制の受動態)
展開式:(They) expected(vt) Lloyd Austin to-inf (他動詞expect/S+V+O+C)
⇒ Lloyd Austin (be) expected(pp) to-inf (受動態/S+V+C)
□ US officials have argued they are trying to ~
構造式:S have argued(pp) that-cl(現在時制の完了形)
展開式:S argue(vt) that-cl(他動詞argue/S+V+O)
⇒ S (have) argued(pp) that-cl(argueの現在完了形)
□ There had been an expectation the White House could impose ~
構造式:There had been an expectation that-cl(過去時制の完了形)
展開式:There is an expectation that-cl(beの現在時制/V+S)
⇒ There (had) been(pp) an expectation that-cl(beの過去完了形)
動詞の活用には7種類あるのですが(do、does、did、doing(現在分詞)、done、to do、doing(動名詞))、その7種類はあくまでも活用(語形変化の元)であって、そのままの形で英文の基本構造の「動詞V」として使用できません。
あくまでも、動詞は「主語S」があっての動詞ですから(nexus法則)、主語の多様な「動作や状態」を主観的にそして客観的に正しく言語表現するためには、動詞は「語形変化」が必要になります。従って、動詞の活用はその「語形変化」の原型ということです。
その「語形変化」を引き起こすもう一つの原因となるのが、「主語の動作や状態」に時間の概念を加えた表現法、すなわち「時制tense」(現在・過去・未来)です。
そこで、上記の最初の展開式は、「過去時制であると同時に受動態」の表現であることから、「be動詞の過去形」と合わせて動詞が「過去分詞」に語形変化をしたのであり、中の展開式は「現在時制であると同時に完了形」の表現であることから、「have動詞」に加えて動詞が「過去分詞」に語形変化をしているものです。そして、最後の展開式は、中の現在完了形の展開式を前提とし、「have動詞」を過去形に語形変化させた表現法になっているのです。
英語と日本語間の翻訳は、一方の日本語には動詞の厳密な語形変化(語形変化だけではなく、表現法そのものの概念も異なる側面がある)が存在しない言語であるために、英語の厳密な言語変換に対する「定型的な日本語表現」は存在しないということです(日本語が世界共通言語になれない原因の一つ)。これが最重要な問題なのです。
対策としては、英文における「主語と述語の構造的・機能的関係」及び「動詞の構造的・機能的関係」の深い知識(でんしゃ理論)を前提として、日本語への訳出を決定するということになるでしょう。この訳出法が原文の真意に最接近するための唯一の方法ではないかと思います。
二、分析②(理論)
上記の解説で述べたように、動詞の語形変化は「現在・過去・未来」という「時制tense」表現の必要性からだけではなく、さらに重要なのは「主語の動作・状態」を動詞を中心として、動詞に係る「付加的構造物」の働きによって表すものであるということです。
その中でも動詞の意味内容に与える重要な要素は、上記したように「時制(tense)」の働きなのです。しかしながら、英語に対する日本語がこのような科学的法則に従って表現する言語でなければ、無論翻訳できませんし、もし翻訳しようとすれば科学理論の突き詰めた領域を超えた「文化を背景とした日本語解釈」の問題が出てくるということです。
従って、この問題は、実は日本語の構造と表現法の特徴から厄介な問題の一つであり、上記した構造式の動詞について「訳語の選択と確定」が極めて難しいということができるのです。
インド・ヨーロッパ語族と日本語の属するウラル・アルタイ語族間の言語変換のアプローチは、ウラル・アルタイ語族の観点からのインド・ヨーロッパ語族の言語構造の分析こそが唯一の方法ではないかという考えで、私の翻訳理論(でんしゃ理論)は組み立てられているのです。
日本語における「時制」一つとっても、その不明瞭さ、つまり時制による表現法の明確な確立がないことから、現在のことか過去のことか未来のことかが判別できない、これは「時制」だけの問題ではないのです。「動作や状態」においても「進行状態、完了状態、経験、結果、さらに継続状態」の明確な区別がないことから、結果として読者の「主観による解釈」が幅を利かす余地が生まれることになるのです。
ですが、この21世紀の社会は江戸時代のような「鎖国社会」ではないのです。ですから、このグローバルな社会を生き抜き、自己の存在を刻むためには、この言語の壁を突き破る必要があるのです。
その視点から、上記した構造式の3つの動詞の語形変化と日本語訳出法を以下に示す「模範訳例」でしっかりと確認してください。