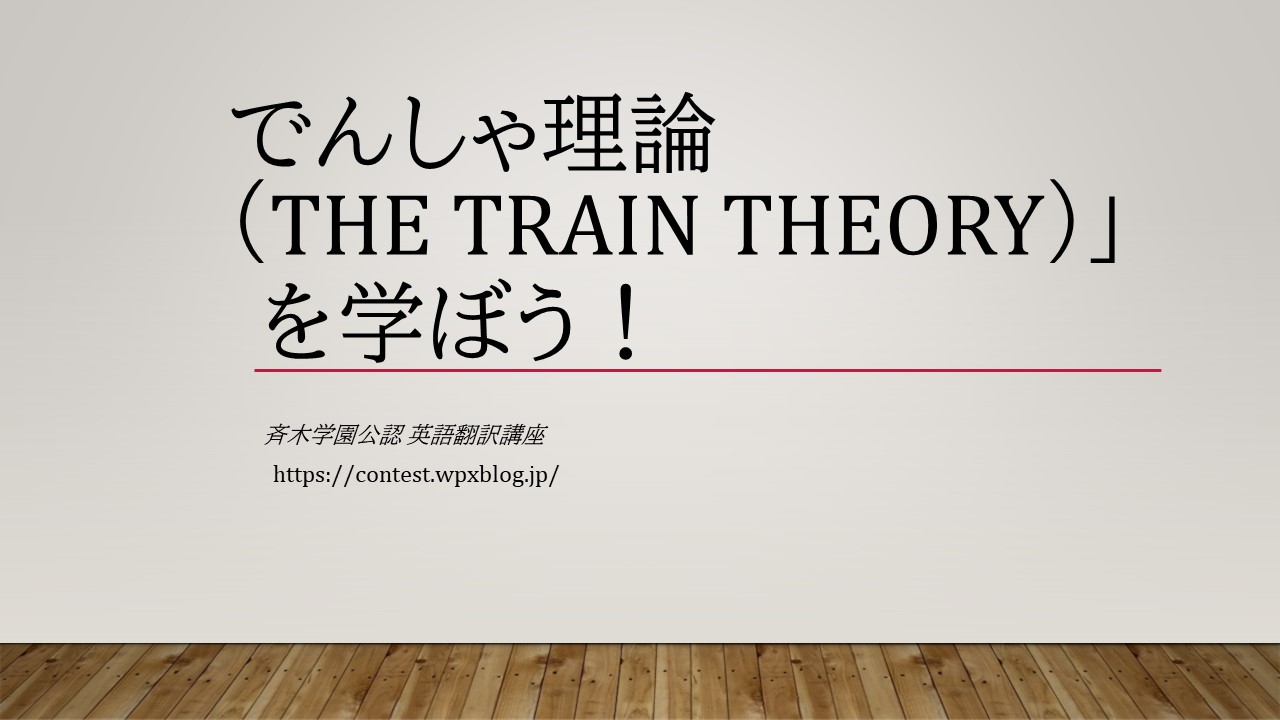「課題文」
CNN spoke with numerous USAID employees around the world who expressed shock as they brace for large swaths of the workforce to be put on leave on Friday night. Hundreds posted abroad have had their lives upended and are waiting for answers on when and how they will return to the US – a massive undertaking expected to cost US taxpayers tens of millions of dollars.
“We are all emotionally distraught,” one USAID diplomat posted overseas told CNN. “We feel like psychological warfare is being waged against us.”
“It’s beyond surreal. It feels like a cruel joke,” said another USAID official posted in a sensitive location. “I am US diplomat, here on a diplomatic passport, and yet I am now kicked off of all embassy systems designed to keep diplomats and their families safe?”
「訳例」
非常に多くのUSAID職員が、金曜夜一時的な解雇に備えている最中、CNNはショックを隠し切れない多くの世界中の職員にインタビューした。海外に派遣された何百人もの職員は、生活が一変させられ、いつどのように米国に帰国することになるか返答を待っているところだ。これは米国の納税者に数千万ドルを負担させるような大掛かりな取り組みだ。
「私たちの誰もが気分的に参っている。」、「私たちに対して心理戦が仕掛けられているようだ。」と、海外に派遣されたある一人のUSAID外交官は、CNNに語った。
「現実離れなんてもんじゃない。悪質な冗談のようだ」、「私は米国の外交官であるし、外交官用のパスポートでここにいる。にもかかわらず、今や私は外交官とその家族を安全に守るためのすべての大使館システムから追い出されている。」と、政情不安な場所に赴任中の別のUSAID職員は語った。
一、 分析① (概説)
今回の解説は、第1段落の ‘CNN spoke with numerous USAID employees around the world who expressed shock as they brace for large swaths of the workforce to be put on leave on Friday night.’
解説のポイントは、「(S+V) for~to構文によるnexus法則」です。
前半の解説では、この課題における「for~to構文によるnexus法則」について、構造的視点から取り上げ、そして後半の解説では、その訳出法について取り上げます。
□ They brace for large swaths of the workforce to be put on leave ~
構造式:(S) brace for+O to-inf (動詞braceとfor~to構文)
展開式1:(S) brace for+O (to-inf) (braceにvi・vt両様の用法)
⇒brace for+O (自動詞braceの用法)
⇒brace to-inf(他動詞braceの用法)
展開式2:(S+V) for+O to-inf(for~to構文)
⇒ O+to-inf(nexus関係が成立するか否か)
上記の構造式から分かるように、動詞braceの直後に前置詞for語句とその後にto不定詞があります。
この表現法は、言うまでもなく動詞braceの「構造的機能」によるものですが、第一の問題は2つある語句が動詞braceとどのような関係にあるのか? そして第二の問題は2つの語句相互間にどのような関係があるのか?ということです。
これを示したのが、展開式1と2で、展開式1は動詞braceがその構造的機能として、直後にfor語句をとる場合もあれば、またto不定詞をとる場合もあることを示しています。
しかしながら、2つのそれぞれの語句相互の関係が分からないと、動詞braceを加えた3者間の訳出はできません。
要するに、動詞braceはその構造的機能として直後にfor語句も取り、同時にto不定詞も取るけれども、いずれの語句を優先させるかは、2つの語句間の「構造的機能」の分析が前提になるということです。これを示しているのが、展開式2です。
もしこの展開式2の構造的機能が成り立たないというときには、to不定詞語句は動詞braceに直接的に繋がる「名詞語句(braceの目的語)」になるということです。
もちろんこの場合、主語they(S)とto不定詞間には「主述関係」が成立することになるのは言うまでもありません(nexus法則)。
二、分析②(理論)
前半の構造分析の中で述べたように、主語と述語、そして直後の前置詞語句と不定詞語句という4つの構造物の関係が分からないと、当然のことながら訳出できません。
その場合問題となるのは、述語の直後にある2つの構造物が、(1)前方の主述とどのような関係にあるのか、また(2)その直後の2つの語句相互間の関係はどうかということです。
原則的な処理として、動詞braceの構造的機能から直後の構造物の関係を決定することができるのですが、この動詞braceは直後にfor語句だけでなく、to不定詞語句をとることもできるために、to不定詞が単純に動詞braceの目的語(不定詞の名詞的用法)になる以外に、for語句との間に「for~to構文」による「主述関係(nexus法則)」という節(clause)構成の働きをしているのかが問題となるのです。
この問題は「構造論・機能論」からいうと、更に難しい問題があるのです。つまり、「他動詞braceはthat-clを目的語にとるか?」という問題ですが、無論取りません。ということになると、主述関係を形成する「for~to構文」における「for語句」はどのような働きをしているのか?ということになります。
結論として、「for語句」は「to不定詞語句」との間に「意味上において主述関係(nexus法則)」を形成するためだけに「挿入された副詞語句」だということです。これを「意味上の主語」と呼びます。