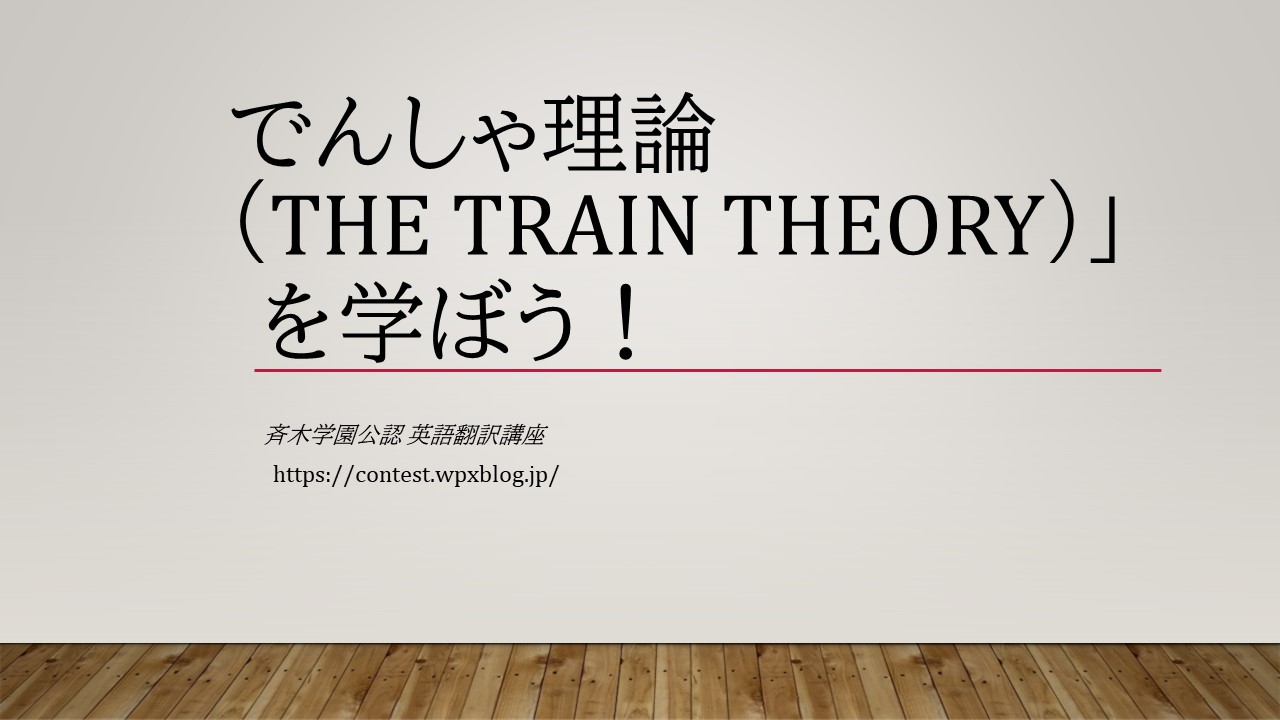「課題文」
A three-day ceasefire in Ukraine that was unilaterally declared by Russian President Vladimir Putin last month has come into effect, as Russia prepares to mark the anniversary of its World War II Victory Day on Friday.
Within three hours, Ukraine’s air force had claimed Russia had launched guided bombs over Sumy in the north of Ukraine, the Reuters news agency reported, adding that it could not independently verify the claims.
A statement from the Kremlin last month said that Putin ordered “all military actions” in Ukraine to be suspended from midnight May 8 to midnight May 11 based on “humanitarian considerations.”
Kyiv rejected the short-term truce when it was first announced. Ukraine’s President Volodymyr Zelensky called Putin’s announcement a “theatrical performance” and reiterated his country’s support for an earlier US proposal for a 30-day ceasefire which Russia has rejected.
「訳例」
ロシアが金曜日に予定する第二次大戦戦勝記念日の準備をする中で、ウラジーミル・プーチン大統領が先月、一方的に宣言したウクライナでの3日間の停戦が発効した。
ロイター通信の報道によると、そのプーチンによる停戦の発効から3時間も経たない内に、ロシアがウクライナ北部のスームィ州全域に向けて誘導爆弾を発射したとウクライナ空軍が主張した。しかし、ロイターはその主張を独自に検証することはできなかったと付け加えた。
先月、ロシア政府が発した声明によると、プーチンはウクライナでの「すべての軍事行動」を「人道的配慮」に基づいて、5月8日夜中の12時から5月11日夜中の12時まで停止するよう命じたということだ。
ウクライナ政府は、その短い停戦が最初に告げられた時点で拒絶した。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、プーチンによる停戦の発表を「芝居がかったパーフォーマンス」と呼び、そしてウクライナは、ロシアが拒絶した30日間の停戦という先のアメリカの提案を支持すると改めて述べた。
一、 分析① (概説)
今回の解説は、以下の通りです。
第1段落の ‘A three-day ceasefire in Ukraine that was unilaterally declared by Russian President Vladimir Putin last month has come into effect, ~’
第2段落の ‘Within three hours, Ukraine’s air force had claimed Russia had launched guided bombs over Sumy ~’
第3段落の ‘A statement from the Kremlin last month said that Putin ordered “all military actions” in Ukraine to be suspended ~’
第4段落の ‘Kyiv rejected the short-term truce when it was first announced.’
解説のポイントは、「段落構成法とは何か?訳出法との関係はどうか?」です。
前半の解説では、この課題について構造的視点から取り上げ、そして後半の解説では、その訳出法について取り上げます。
□(抜粋1) A three-day ceasefire in Ukraine ~ has come into effect, ~
構造式:S+V(第一段落の文頭表現)
□(抜粋2) Within three hours, ~ Russia had launched guided bombs ~
構造式:prep+O, S+V+O(第二段落の文頭表現)
□(抜粋3) A statement from the Kremlin last month said that Putin ordered
“all military actions” in Ukraine to be suspended ~
構造式:S1 said that S2+V+O+C(第三段落の文頭表現)
□(抜粋4) Kyiv rejected the short-term truce when it was first announced.
構造式:S+V+O(第四段落の文頭表現)
今回の「段落構成法」については、この講座のみならず拙著「実践から学ぶ~」の中で説明していますが、言うまでもなく「学校文法」で取り上げられていないために、どの応募答案の訳文を見ても翻訳としての条件が満たされていないために、改めて取り上げることにしました。
先ず「段落構成法」の理論的位置づけは、翻訳における三段階「構造分析⇒訳出⇒日本語表現」の「構造分析」の中の一つの作業に関する法則です。
上記のように四段落ある文頭の表現を抜粋しましたが、「段落構成法」はその文頭表現の前提として段落ごとにそれぞれ特定の大きな役割があるということです。その特定の役割が上記の文頭表現法に影響しているということです。
—————————
(抜粋1)のテーマは、「ceasefire has come into effect」で始まり、それを受けて(抜粋2)のテーマは、しかし「prep+O, S+V+O」となった。それを受けて(抜粋3)のテーマは、そもそもの原因は「said that-cl」で表され、そしてそれを受けて(抜粋4)のテーマは、「S rejected +O」というのが真相だった、という論理展開になっています。
—————————
以上の点線内は、段落ごとの流れを文頭表現を中心にして表したものです。
このように、仮に「段落構成法」の法則を知らなくても、各段落の「文頭表現法(システム)を掴むだけで英文全体の筆者の意図をあらかた理解することができるのです。勿論、上記のことから分かるように、段落ごとの役割を考慮して接続語を「追加」しているのですが・・・。
要するに、この技術は言うまでもなく、「段落構成法」の法則が前提となっていることであり、訳出との関係は、以下の解説で取り上げます。
—————————————–
二、分析②(理論)
前半の解説から分かるように、英語表現は日本語の表現法とは異なり、一文一文の英文構造に加えて、更に段落に分けてそれぞれの段落に一定の役割を持たせ、それらが一体を成して筆者の意図を「論理的に表現する」方法をとっているのです。
その後者の表現法を「段落構成法」と呼んでいるのです。要するに、このような論理展開法を歴史的に遡ればギリシャ時代の論理学、すなわち「三段論法」に基づいているのです。「大前提⇒小前提⇒結論」によって自己主張を科学的に証明する英語表現法、これが「段落構成法」ということになります。
「段落構成法」をこの三段論法に合わせて表現すると、「前文(筆者の問題提起)⇒本文(具体的事例によって前文を証明ないしは反対証明(反証)する)⇒結論(自己主張や行動の正当性)」ということになります。
このように、第一段落を上記の「前文」として捉え、第二・第三段落を「本文」として捉え、そして最後の段落を「結論」として捉えるならば、前半の点線内で私が示した各段落の文頭の「接続表現(しかし、そもそも)」の何たるかが分かるのではないでしょうか。
であれば、もう一歩進んで考えると、「でんしゃ理論(構造論・機能論)」における「接続関係」は「主述関係(nexus法則)」を前提とした論理であることから、後文を訳出するときには「前文の動詞」の表現法との関係を考慮に入れる必要があるということになります。
まとめると、(1)前文の動詞表現と後文の文頭表現、そして(2)各段落の特定の役割と段落相互の相互関係を考慮することによって、文意の一貫した簡潔な翻訳が可能になるということですね。