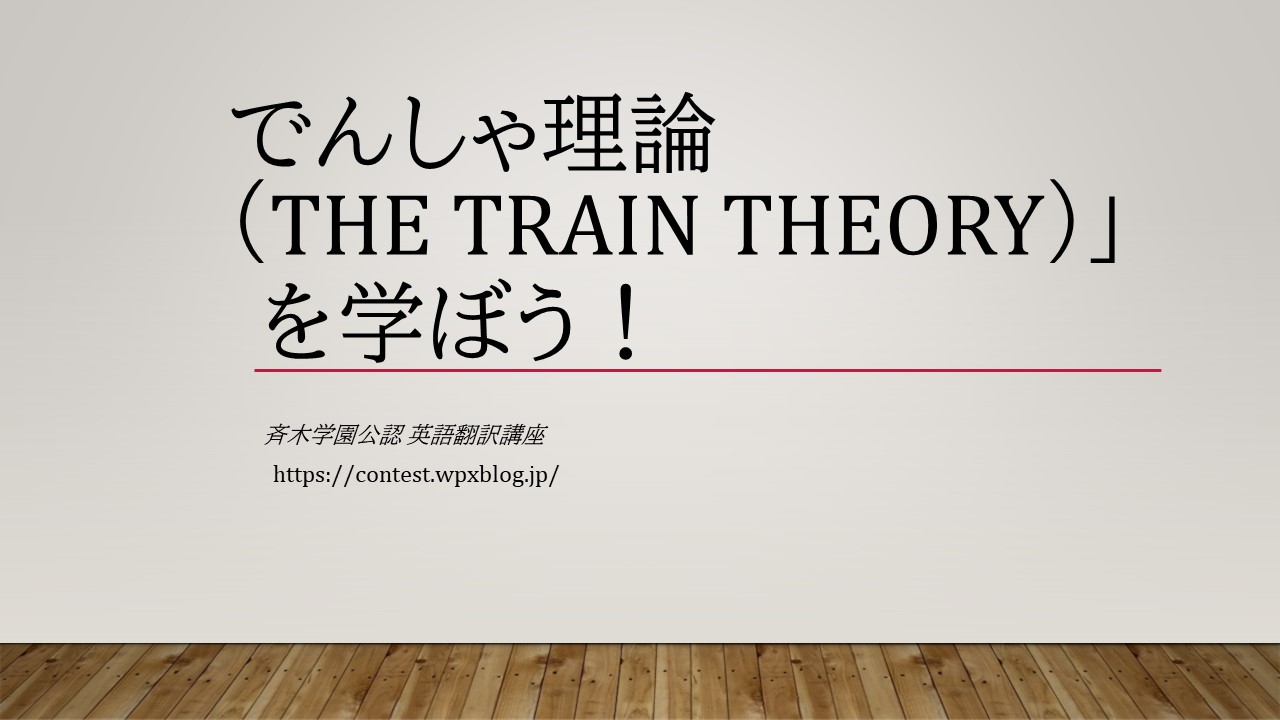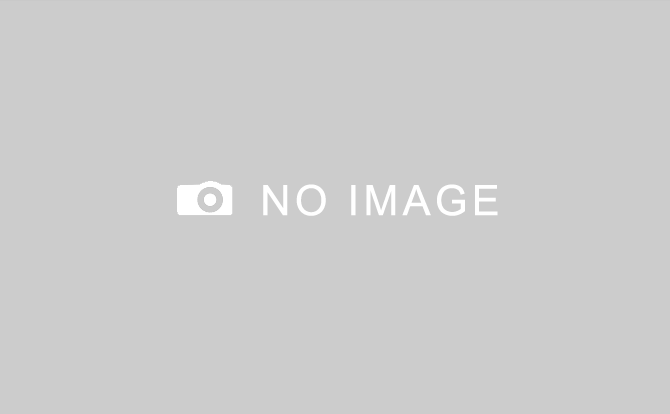「課題文」
President Donald Trump on Wednesday announced sweeping and substantial tariffs on India, one of America’s most important trading partners. In addition to a 25% tariff that is set to go into effect Thursday, Trump also announced an additional 25% tariff on India that will go into effect later this month as punishment for importing Russian oil and gas.
Those combined penalties would bring the total tariff on goods imported from the world’s fifth-largest economy to a whopping 50% – among the highest the US charges.
The latest executive order, according to a document posted on the White House website, represents an escalation of his trade battle with New Delhi and his first use of so-called secondary sanctions on countries the US says are fueling Moscow’s war machine.
「訳例」
ドナルド・トランプ大統領は水曜日、米国の最も重要な貿易相手国の一つであるインドに対する広範に及ぶ大幅な関税を発表した。つまり、トランプ氏は、木曜日に発効する予定の25%の関税に加えて、ロシア産の石油とガスを輸入していることへの懲罰として今月中に発効するインドに対する25%の追加関税を発表した。
これら2つの関税が賦課されれば、世界第五位の経済大国からの輸入品の関税率の合計は、何と50%まで跳ね上がることになる。これは、米国が賦課する関税の中で最も高い部類になる。
今回の大統領令は、ホワイトハウスのウェブサイトに掲載された文書によれば、インド政府との貿易摩擦の激化とロシアの軍事力を支援していると米国政府が言う国々に対するいわゆる「二次制裁」をトランプ氏が初めて科すことを示している。
———————————————–
一、分析①(概説)
第3段落の ‘The latest executive order ~ represents ~ his first use of so-called secondary sanctions on countries the US says are fueling Moscow’s war machine.
解説のポイントは、「関係詞節内の挿入語句・節」です。
前半の解説では、この課題について構造的視点から取り上げ、後半の解説では、その訳出法について取り上げます。
□ 構造式:S1+V1+O1 the US says V2+O2(挿入節)
⇒展開式1:S1+V1+O1 (that) the US says V2+O2(省略語の補充)
⇒展開式2:S1+V1+O1 that(S2) S3+V3 V2+O2(挿入節のある構造式)
⇒展開式3:that(S2) S3+V3 V2+O2
⇒ that(rel.pron) S3+V3 that(conj) they(S2)+V2+O2(関係詞節内の構造式)
上記の構造式と展開式から分かるように、幾つかの省略語があり、それが文章構造を分かりにくくしていると同時に、反面それらの省略語のおかげで筆者の伝達内容が明確になる構造になっていることを知ってもらいたいと思います。
文章構造が複雑になっていると感じるのは、欧米語の特徴である「主述関係(nexus法則)」とその法則を前提とした各種の「接続関係」を共通した形で持たない言語の我々アジア文化の民族であって、欧米語の大きな2つの特徴である「主述関係(nexus法則)」と「接続関係」をしっかりと学べば問題ありません。
また、文中の省略語の存在によって、筆者の文意が明瞭になるという側面も理解できるということです。例えば、展開式3から省略語の存在と挿入語句の働きによって、主節と関係詞節の間の「主従関係」という効力関係において、関係詞節が必ずしも主節に対して「従たる地位」にあるのではなく、「同等ないしは主たる地位」にもなりうることが理解できると思います。
この問題は、すでにこの講座の中でも、また拙著(実践から~)の中でも取り上げたことのある難解な問題です。この問題の基本形は下記の通りです。
□ S1+V1(vt) that S2+V2 (that節を伴う主節と従属節の主従関係)
結論だけを言うと、この英文構造は実質的にとらえると、主節と従属節の間の関係を実質的に見ると、「主従関係」という効力関係があるのではなく、主節は従属節の単なる「構造的な導入表現法」ではないか?文意の中心は従属節にあるのではないか?(自説)というものです。この問題は、「接続関係」の問題へと転じるのでここでの説明は控えておきます。
———————————————–
二、分析②(理論)
上記の解説から、主節と関係詞節間の効力関係において関係詞節の効力が仮に主節と「同等ないしは主たる地位」にあるとしても、訳出する場合には日本語表現法において主節の本動詞は文末に配置されることから、「訳し下げる」のではなく「訳し上げる」ようにしなければなりません。これが基本です。
しかし、主節を「導入表現法」として捉えることから、「訳し下げる」ことも不可能ではないのですが、その場合にはその主節を「副詞語句化」することができるかどうかの問題があります。構造的には後続表現法を決定する一方で、意味論的には後続表現の補助の役割を持つことになるからです。
従って、課題文の挿入語句・節である「the US says」の訳出は、基本的には関係詞節を訳出した後に、それを受ける形で訳出する、要するに「訳し上げる」のが基本ですが、上記したように「副詞語句化」することが可能であれば「訳し下げる」ことも理論上できないわけではありません。
しかし、関係詞節内の「挿入語句・節」の場合にも理論上「訳し下げる」ことも可能ですが、私の経験上そのような場合の記憶がありません。ということは、このような形態の表現法においては、主節の働きとして「副詞語句化」の働きはないということになります。
結論として、この課題文のように「関係詞節内の挿入語句・節」を訳出する場合には、基本的に「訳し上げる」方法を採用するということです。
以上の解説を「模範訳例」で確認してください。