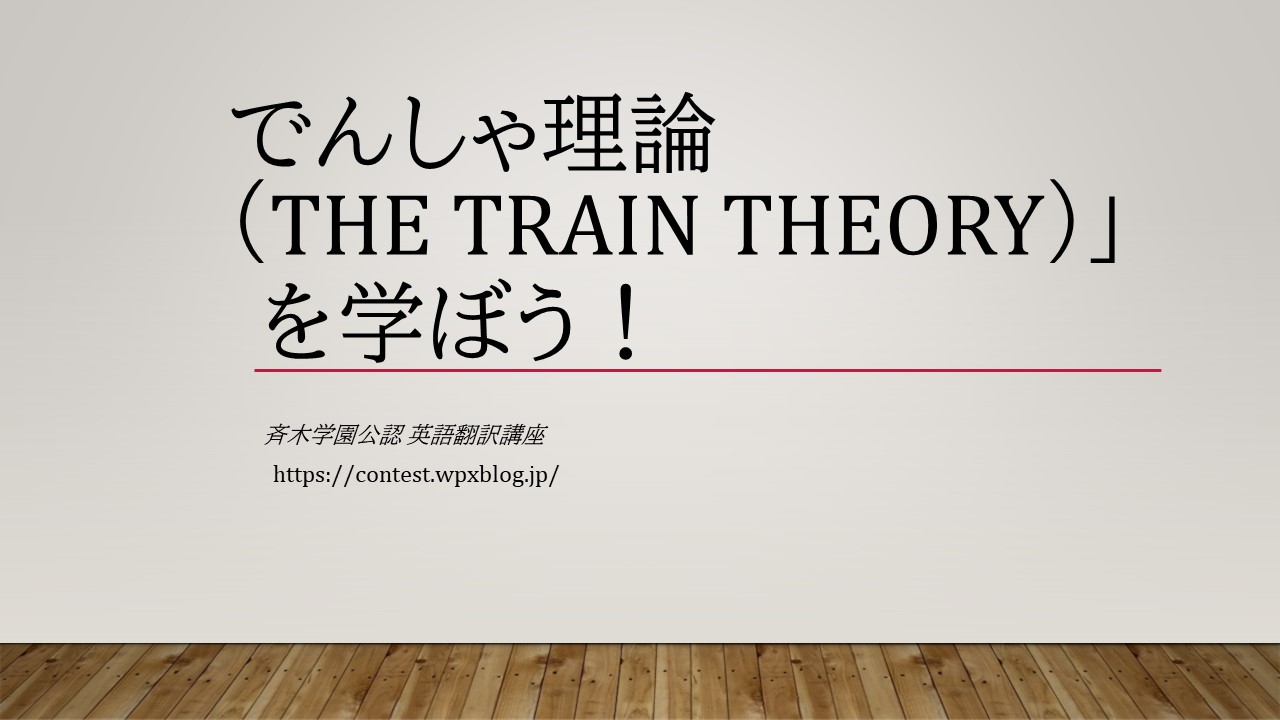「課題文」
President Trump is not only working to stop a transition away from fossil fuels in the United States, he is pressuring other countries to relax their pledges to fight climate change and instead burn more oil, gas and coal.
Mr. Trump, who has joined with Republicans in Congress to shred federal support for electric vehicles and for solar and wind energy, is applying tariffs, levies and other mechanisms of the world’s biggest economy to induce other countries to burn more fossil fuels. His animus is particularly focused on the wind industry, which is a well-established and growing source of electricity in several European countries as well as in China and Brazil.
Two weeks ago, the administration promised to punish countries ? by applying tariffs, visa restrictions and port fees ? that vote for a global agreement to slash greenhouse gas emissions from the shipping sector.
音声解説はこちらからどうぞ。
「訳例」
トランプ大統領は、米国において化石燃料からの脱却を阻止しようとしているだけではない。他国に対しても、気候変動と闘う公約を緩和するように、それどころか石油やガス、そして石炭をこれまで以上に消費するように圧力をかけている。
トランプ氏は、EVや太陽光、そして風力発電への連邦政府の支援を打ち切るために、これまで議会で共和党と共闘してきたが、他国に対しても化石燃料をさらに消費させるために、関税や徴税、その他世界最大の経済力の仕組みを適用している。特に、トランプ氏の狙いは風力産業に集中している。というのは、風力は中国やブラジルだけでなく、ヨーロッパの数ヶ国でも確立され、成長過程にある電力源であるからだ。
2週間前、トランプ政権は、「関税、ビザの発給規制、港湾の使用料を適用することによって」、物流分野が排出する温室効果ガスを大幅に削減するためのグローバル協定に賛成する国々に対して制裁を加えることを約束した。
———————————————–
一、分析①(概説)
第3段落: The administration promised to punish countries ? by applying tariffs, visa restrictions and port fees ? that vote for a global agreement to slash greenhouse gas emissions from the shipping sector.
解説のポイントは、「関係詞の直前にある挿入語句」です。
前半の解説では、この課題について構造的視点から取り上げ、そして後半の解説では、その訳出法について取り上げます。
□ 構造式:S+V1+O1 – by+O2 – that V2 for+O3(関係詞直前の挿入語句)
⇒展開式:S+V1+O1(先行詞) prep+O2 that V2 (先行詞と関係詞の間の語句)
「関係詞の直前にある挿入語句」を訳出に際してどのように処理するか?については、すでに拙著「実践から~」の中で取り上げていますが、その内容を”でんしゃ理論”による「構造論・機能論」からもう少し掘り下げてみようと思います。
上記の構造式から分かるように関係詞の直前にある語句の形態は、前後に「emダッシュ記号」を用いた「挿入語句」になっています。一般的な表現法は、展開式で示した表現法であって、ダッシュ記号まで用いて「挿入語句形式」にするものではありません。
その理由は何か?ということです。その理由を求める方法の一つが、「emダッシュ記号」を前後に配置したことです。本来、「ダッシュ記号」の機能は「前節からある種の「独立」を図りつつ、同時に前記事項の注記・追記・説明、そして筆者の見解」(第73話)ですが、その「ある種の独立」が「強調」として働いたのが、この課題なのです。
———————————————–
二、分析②(理論)
上記の展開式が示すように、関係詞と先行詞の間にある「前置詞語句」が「挿入語句」であるか否かに関わらず、訳出法において一般的にどのように処理されるべきかについて取り上げます。
この処理法は、「主要構造物と付加的構造物」における訳出上の問題点に関わるのです。つまり、主節である前節、上記の展開式でいえば「S+V1+O1」が「主要構造物」であり、この「主要構造物」に対して2つ「付加的構造物」、上記の展開式でいえば前置詞語句の「prep+O2」と関係詞節「that V2」があるのです。
そこで、訳出する場合、「主要構造物」の「本動詞」に向けて、これら2つの「付加的構造物」を訳し上げることになるのですが、その場合2つの「付加的構造物」のうちいずれを先に訳出するのか?これが問題となるのです。
もし前置詞語句の「前置詞」が直前の「先行詞O1」による構造的機能の働きで存在しているのであれば、前置詞語句と先行詞O1が「意味上の一体性」を持つことになり、従って訳出は関係詞節である「付加的構造物」の方を先に訳出することになります。
しかし、前置詞と先行詞との間に先行詞による構造的機能による一体性がない場合には、その前置詞は「主要構造物」の「本動詞」との関係で訳出することになり、従って訳出は前置詞語句である「付加的構造物」の方を先に訳出することになります。
そこで、課題の表現法であるダッシュ記号を用いた「付加的構造物」の処理ですが、先に述べたようにこの記号の構造的機能は、ある種の「強調」であるために、直前の先行詞O1との間の一体性を排除したものであり、結果として「本動詞との一体性」を「強調」したものと捉えることができます。
ということは、訳出は前置詞語句である「付加的構造物」の方を先に訳出することになるということです。