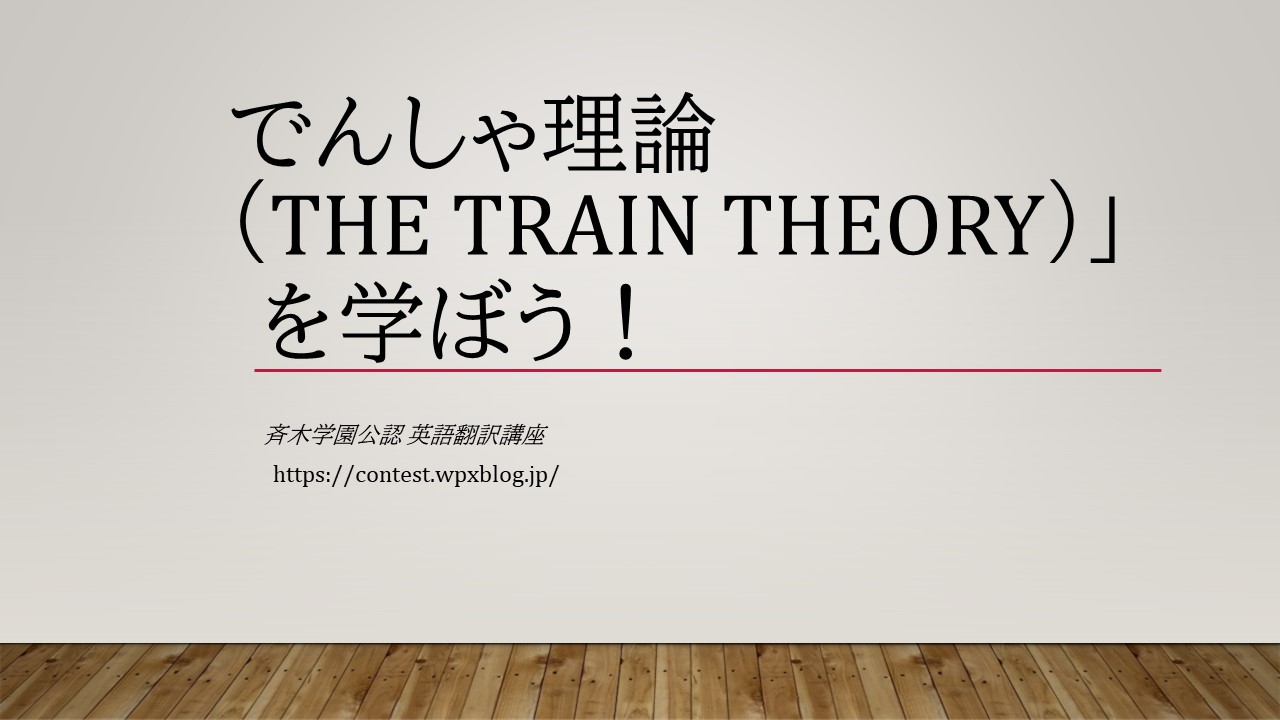「課題文」
In response to the imposition of new, unjustified US tariffs on EU steel and aluminium imports, the Commission has launched swift and proportionate countermeasures on US imports into the EU.
The Commission regrets the US decision to impose such tariffs, considering them unjustified, disruptive to transatlantic trade, and harmful to businesses and consumers, often resulting in higher prices.
The Commission’s response is carefully calibrated, based on a two-step approach:
First, the Commission will allow the suspension of existing 2018 and 2020 countermeasures against the US to lapse on 1 April. These countermeasures target a range of US products that respond to the economic harm done on €8 billion of EU steel and aluminium exports.
Second, in response to new US tariffs affecting more than €18 billion of EU exports, the Commission is putting forward a package of new countermeasures on US exports. They will come into force by mid-April, following consultation of Member States and stakeholders.
「訳例」
欧州委員会は、EUの鋼鉄とアルミニウムの米国への輸入に対する新たにして不当な関税に対応して、米国からのEUへの輸入に対する即応した対抗措置に着手した。
欧州委員会は、そのような関税は不当であり、環大西洋貿易に壊滅的な悪影響を及ぼし、企業や消費者に損害を与え、往々にして物価の高騰を招くことになることを考えて、米国によるかかる決定を遺憾に思っている。
欧州委員会の対応は、2段階方式に基づいて慎重に調整されることになる。
第一段階として、欧州委員会は、2018年と2020年に設けられた米国に対する現行の対抗措置の一時停止を4月1日に無効にする。この対抗措置は、80億ユーロ相当のEUの鉄鋼とアルミニウムの輸出品が被った経済的損害に匹敵する広範な米国製品が対象である。
第二段階として、欧州委員会は、180億ユーロ以上のEUの輸出品に影響を与える新たな米国の関税に対応して、米国の輸出品に対する新たな包括的な対抗措置を打ち出そうとしている。その措置は、EU加盟諸国および利害関係国との協議を経て、4月中旬までに施行される運びだ。
———————————————–
一、分析①(概説)
今回の解説は、第4段落の ‘The Commission will allow the suspension of existing 2018 and 2020 countermeasures against the US to lapse on 1 April.’
解説のポイントは、「動詞allowとto不定詞の関係」です。
前半の解説では、この課題における「動詞allowとto不定詞の関係」について、構造的視点から取り上げ、そして後半の解説では、その訳出法について取り上げます。
□ The Commission allows the suspension of 2018 and 2020 countermeasures
against the US to lapse ~
構造式:(S) allow +O to-inf (動詞allowとto-inf)
展開式1:allow +O to-inf (V+O+C / O = C)
展開式2:(S) allow +O (S1+V1) O +to-inf (O = C / S2+V2)
上記の「展開式1」から分かるように、動詞allowの直後に目的語とto不定詞があります。この目的語の直後の「to不定詞」の構造的役割が何であるかは、すべて動詞allowの「構造的機能」によって決定されるのです。
結論的に言うと、上記の展開式から分かるように、その不定詞は動詞allowの「目的格補語」であり、その性質は「不定詞の名詞的用法」ということになります。そのことから、この動詞allowは「不完全他動詞」の構造的機能を持っていることになります。
目的語の直後の「to不定詞」の性質がすべて「名詞的用法」であるわけではなく、「形容詞的用法」のこともあれば、「副詞的用法」のこともあるのです。
そのような違いは、もちろん動詞の「構造的機能」や不定詞の直前にある目的語の「名詞」によって決定されるのですが、英語nativeではない我々にはその機能を動詞を見ただけで決定することは難しいものがあります。しかし、「展開式1」の括弧書きの構造式で示したように、英文構造の基本的法則である「nexus法則」によって決定することができるのです。
つまり、上記したように、その「to不定詞」が「目的格補語」であれば、目的語Oと目的格補語Cとの間には、「繋合詞be」の省略が成り立つのです。
そのことから、この動詞allowは「不完全他動詞」であることになり、後方の「解説」の中で示すように含意には「作為動詞」の意味内容があり、そして「to不定詞」の性質は「不定詞の名詞的用法(be動詞の名詞補語)」になるのです。
ここで、「作為動詞」と「使役動詞」の意味内容と構造についていうと、基本的な意味内容は同一である(~させる)が、構造は不同である。つまり、前者の目的格補語の構造は「to不定詞」であることに対して、後者は「toのない原形不定詞」だということです。
———————————————–
二、分析②(理論)
上記したように、to不定詞を目的格補語にとる不完全他動詞allowの訳出は、目的語と目的格補語との間に「繋合詞be動詞」を介して「nexus法則」が成り立つことから、「OがCである」と訳出しても、根本的な意味を崩すものではありません。
しかし、目的語と目的格補語の間に「nexus法則」が成り立つかどうかは、あくまでも目的格補語である「to不定詞」が本動詞allowの構造的機能によるものであるかどうかの判定基準であって、それが動詞allowを含めた訳出そのものに反映されるわけではありません。
少し突っ込んで言うと、上記の「展開式2」で示したように、一文の中に2つの「nexus関係」が成立しており、目的語と目的格補語との関係(S2+V2)は本動詞V1が構成する主述関係とは別のものだということです。
もっとも、この「nexus法則」が成立することは事実であることから、仮に「OがCである」という訳出を前提として、この課題の本動詞allowを含めて訳出することも不可能ではありません。
要するに、「OがCであることを許す(許可する)」と訳出しても、意味の本質からはずれたものにはならないということです。
正式な訳出としては、作為動詞allowを前提とした直接訳は、「目的語に対し許可を与えて~させる」というものです。
他の作為動詞には「強制や命令や依頼などによって~させる」という含意のものがあります。
例えば、compell(強制)やforbid(命令)や ask(依頼)などです。