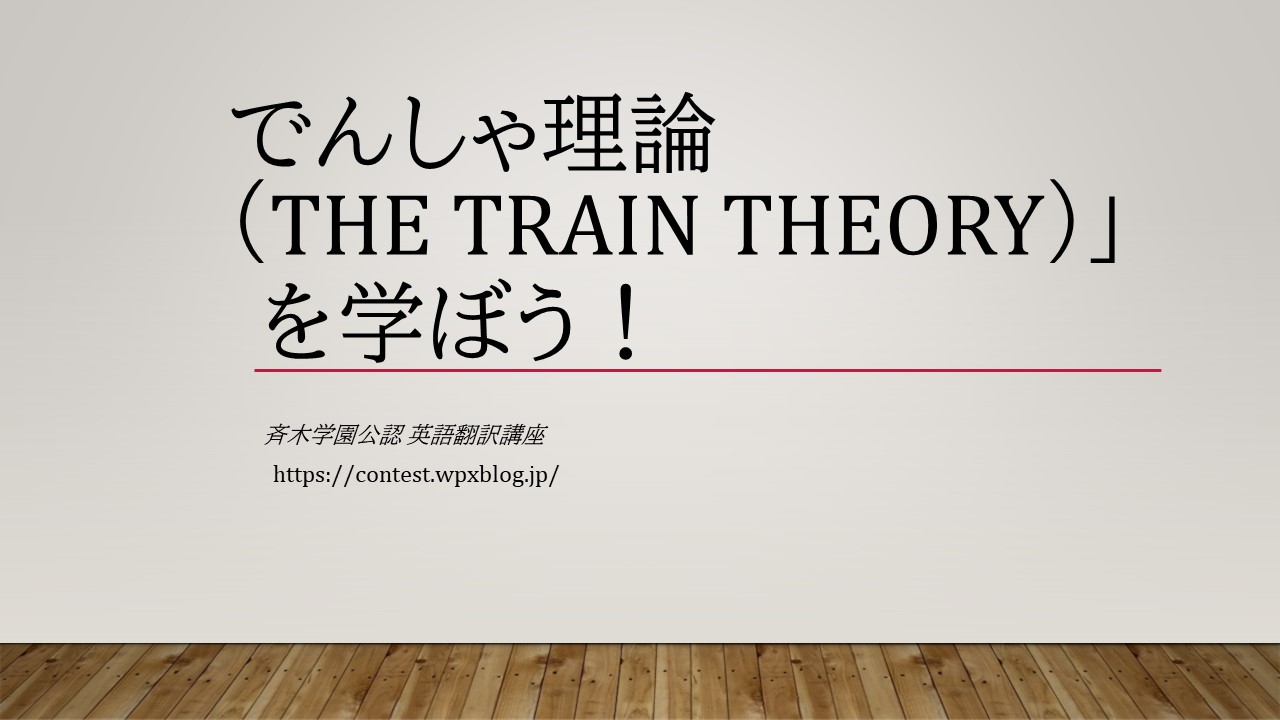「課題文」
During President Trump’s first term, Ukraine worried that Mr. Trump might recognize Russian control over Crimea, the Ukrainian peninsula Moscow forcibly seized in early 2014.
As a candidate, Mr. Trump had said he would “take a look” at the matter, even though the Obama administration and America’s Western allies had rejected Russia’s annexation of the strategic territory. Mr. Trump even mused that “the people of Crimea, from what I’ve heard, would rather be with Russia.”
But Mr. Trump never followed through and even doubled down against Moscow. In July 2018, Secretary of State Mike Pompeo issued an official “Crimea Declaration” pledging that the nonrecognition policy would remain “until Ukraine’s territorial integrity is restored.”
Now, in his effort to negotiate an end to the war between Russia and Ukraine, Mr. Trump is prepared to walk away from that declaration — and more than a decade of American policy.
音声解説はこちらです。
「訳例」
第一次トランプ政権のとき、ウクライナは、2014年初頭にロシア政府が力ずくで奪い取ったウクライナ領の半島、クリミアのロシア支配をトランプ氏が承認するのではないかと憂慮していた。
実際、彼が大統領選に立候補していたとき、オバマ政権とアメリカの西側同盟諸国がロシアによるこの戦略的領土の併合を拒否していたにもかかわらず、このクリミアの併合問題を「見直す」と述べ、しかも「クリミアの住民は、聞くところによるとロシアに好意を抱いているようだ」とさえ語っていた。
しかしその後、トランプ氏はその見解を貫き通すどころか、反対にロシア政府に対する批判を強めた。2018年7月には、マイク・ポンぺオ国務長官が、「ウクライナの領土の一体性が回復されるまで」クリミア併合の不承認政策は変更しない、とする公式の「クリミア宣言」を発表した。
ところが現在、トランプ氏はロシアとウクライナの戦争終結の交渉に当たって、そのクリミア宣言、つまり10年以上にわたるアメリカのこの政策から手を引こうとしているのだ。
———————————————–
一、分析①(概説)
第4段落: Mr. Trump is prepared to walk away from that declaration — and more than a
decade of American policy.
今回の課題文のテーマは、「述語にto不定詞を伴う表現法と助動詞の関係」です。
□ 構造式:(S) is prepared to walk away from ~(助動詞と本動詞の区分)
展開式:(S) be prepared to + V (auxil-v +V / 単なる受動態か?)
類例:(S) be going to + V(be going to = will)
今回のテーマの「述部にto不定詞を伴う表現法と助動詞の関係」については、すでに「でんしゃ理論や拙著・実践から学ぶ~」で取り上げました。今回はその見解をもう少し掘り下げて解説します。
この「助動詞と本動詞」の問題は、助動詞の存在理由そのものについて、私の見解が一般学説とは異なっているために、以下その違いを構造的に述べ、後半の解説では助動詞の存在理由とそれに基づく訳出法の概略を明らかにしようと思います。
先ず構造について言えば、助動詞の構造には幾つかの形態があるために、今回取り上げるのは固定の助動詞、例えば「canやmust」ではなく、述部に「to-inf」を伴うような構造の助動詞について取り上げます。
助動詞の基本的な「構造的機能」は、本動詞の「構造的機能」であるセンテンスの構造を決定する中核的機能(意味論的に言うと、主語の動作や状態)に対して、それを「補助」するというか、「別の視点」(主語の視点ではなく話者・筆者の視点)からの追加的な表現法です。
従って、構造的に見ると本動詞の直前にあって、本動詞と一体を成し、主語に対する「述語」を形成するということになります。ということは、助動詞と本動詞は相互に「独立」した存在であって、それが述語として一体を成すのかというと、そうではありません。
固定の助動詞とは異なって、多様な種類の助動詞は元々「本動詞の進化と本動詞からの分離」したものだからです。つまり、助動詞は「本動詞の変化形」だということでもあるからです。
それでは、本動詞と区別する「基準」は何か?ということになりますが、構造的に言うと上記の展開式が示すように「to-inf」の存在が一つの基準です。つまり、2つの動詞の一方が助動詞であり、他方が本動詞である場合、その一体化は「to-inf」による方法しかありません。
その場合、上記の「展開式と類例」は「受動態と進行形」ではなく「助動詞」なのだとすると、もう一つの判断基準が必要となります。要するに、助動詞の「意味上の実質的な働き」です。それが、私の見解である「話者(筆者)の主観的傾向(心的態度)」ということになります。
要するに、2つの条件(構造と主語の主観)によって、助動詞であるか否かの判断をするということです。
———————————————–
二、分析②(理論)
前半の解説で、上記の展開式と類例は「受動態と進行形」ではなく「助動詞」なのだとする2つ目の判断基準は、助動詞の「実質的な働き」であり、それは「話者(筆者)の主観的傾向(心的態度)」であると述べました。
つまり、本動詞によって「主語の動作や状態」を明らかにし、そして助動詞によって「主語の動作や状態」に対する「話者(筆者)の主観的傾向(心的態度)」を加えるということです。
ということは、本動詞は「主語の事実表現の働き」であり、助動詞は「話者(筆者)の主観表現の働き」であることになります。また、主語は文字化され文章中に現れますが、話者(筆者)は文字化されないために、翻訳に際しては原文における「話者(筆者)は誰か?」を常に確認しておかねばなりません。そうしないと、助動詞の適切な訳出ができないからです。
さて、固定の助動詞以外の「to-inf」を持つ助動詞にはどんなものがあるかですが、例えば「need (to)やdare (to)、あるいはought to」などが典型的ですが、それ以外にも上記の展開式や類例など「2つの基準」に従って特定することができます。
もっとも、「本動詞の進化と本動詞からの分離」を明確に示すものと、そうではなく同じ表現法であっても「主述関係」における状況次第で、本動詞になったり助動詞になったりする、いわゆる両方の機能を持つ表現法もあるということです。