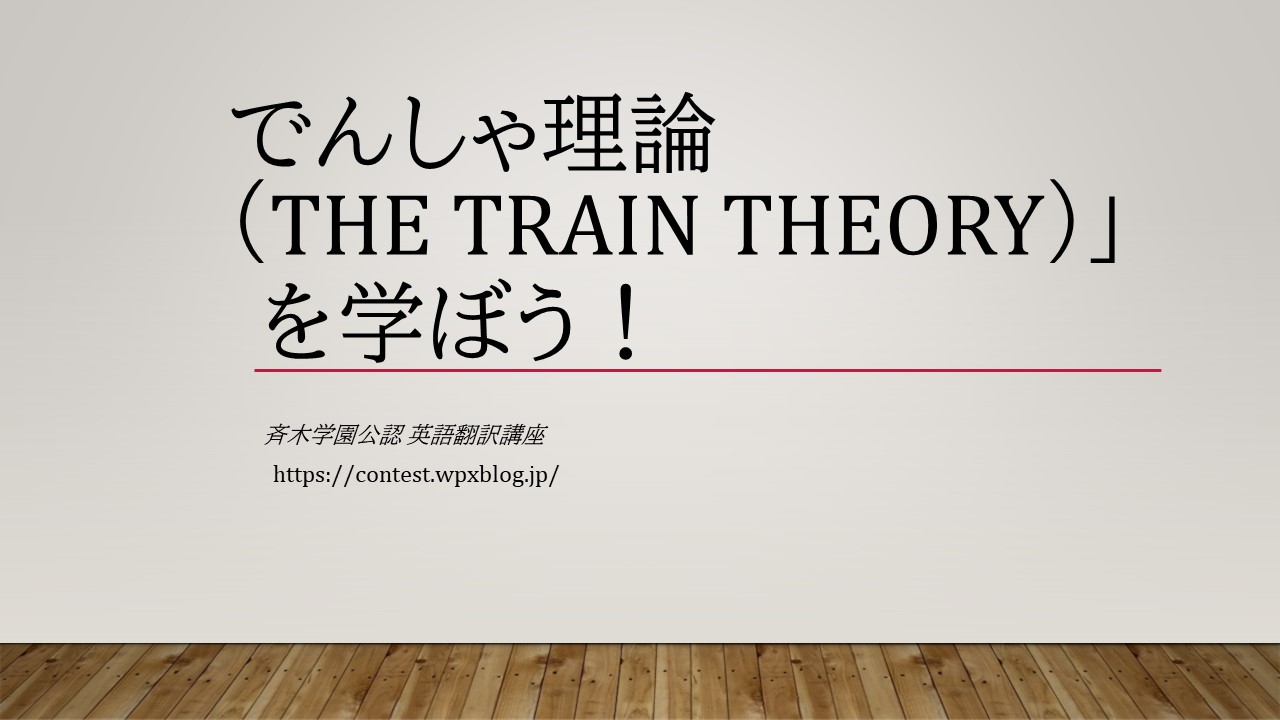「課題文」
Three weeks after Chancellor Friedrich Merz took over as the leader of Germany, President Volodymyr Zelensky of Ukraine will visit him in Berlin on Wednesday.
The Ukrainian leader’s visit will be his third meeting with Mr. Merz in as many weeks and underscores Mr. Merz’s focus on the war in Ukraine, as he seeks to reestablish German leadership among European allies in the face of weakening U.S. commitments to NATO.
Mr. Zelensky will meet with Mr. Merz in the Chancellery, Germany’s executive office, and the two men will hold a joint news conference in the afternoon. Later, the Ukrainian leader is expected to have talks with President Frank-Walter Steinmeier in Bellevue, the presidential palace.
Large sections of the government district in Berlin are expected to be cordoned off by the police on Wednesday, as was the case during previous visits by the Ukrainian president.
「訳例」
フリードリヒ・メルツ首相がドイツの指導者に就任して3週間後、ウクライナのヴォロディミル・ゼレンスキー大統領は水曜日、ベルリンでメルツ首相を訪問する予定だ。
ウクライナの指導者による今回の訪問は、メルツ氏との3週間に連続3度目の会談ということになり、メルツ氏がウクライナ戦争に強い関心を抱いていることを際立たせている。というのも、米国のNATO(北大西洋条約機構)への関与が弱まる中で、メルツ氏は欧州の同盟国の間でドイツの主導的地位を再構築する狙いがあるからだ。
ゼレンスキー氏は、ドイツの連邦首相府でメルツ氏と会談し、午後彼らは共同記者会見に臨む予定だ。その後、ゼレンスキー氏はベルビュー宮殿(大統領府)でフランク=ヴァルター・シュタインマイヤー大統領と会談すると思われる。
ベルリンの官庁街の大部分は水曜日、ゼレンスキー氏の以前の訪問時と同様、警察によって道路が封鎖されると思われる。
———————————————–
一、分析①(概説)
第2段落: The Ukrainian leader’s visit will be his third meeting with ~ and underscores Mr. Merz’s focus on ~, as he seeks to reestablish ~
今回の課題文のテーマは、「as節は、主要構造物に対する付加的構造物か?」です。
□ 構造式1:S(~ leader’s visit) be+C and V+O, as-cl(andとカンマ記号の意味)
□ 構造式2:S1(物主語)+V1+C and V2+O, as S2+V3(構造式1の抽象化)
上記の構造式2を構造論的に分析する場合、構造式1で示したように接続詞andとカンマ記号の存在によって、2つの分析が可能となります。
1つは、カンマ記号の存在によって、1つの主語に対して2つの動詞があり、これが「主要構造物」を構成し、as節はそれに対する「付加的構造物」であるという捉え方です。
もう1つは、上記の分析の前半はそうであっても、後半のas節も一つの「主要構造物」ではないかという捉え方です。
このいずれかの解決法は、一つしかありません。何度も言うように、接続詞asを中心として「前節の主述関係と後節の主述関係の論理的比較」です。その場合、特に注目しなければならないのは、両者の「動詞相互の関係」を論理的に比較することなのです。
この課題文でいうと、前節の動詞は「事実」を明示しており、それに対して後節の動詞の「主語の意思(私見では筆者の主観的傾向)」と論理的に比較するとどうなるでしょうか?
要するに、as節は前節の「間接的な理由・原因」を表しているということですね。そうであれば、as節は「付加的構造物ではなく、もう一つの主要構造物(正確には、主要構造物に近い)」と捉えることができるのです。
その訳出法は、以下の解説で行います。
ところが、面白いことに、ほとんどの答案がas節を直前の動詞underscoreにのみ接続する「付加的構造物」ととらえていたのです。不思議にも、前の述語will beに接続するとはとらえていないのです。接続詞andがあるにもかかわらず・・・。
これは、接続詞andとカンマ記号の構造的機能を無視した分析だということになります。これは、翻訳作業の第一step(構造分析法)が理解されていないことを示しています。
———————————————–
二、分析②(理論)
上記の構造分析で分かるように、接続詞andやカンマ記号の構造的機能を理解できない状態で科学的な翻訳はできません。要するに、暗記中心の翻訳には何の科学的根拠もないからです。
上記の構造式1と2でいうと、等位接続詞andが2つの述部をつないでいることから、仮にas節の接続詞asが従属接続詞だとしても、そうであれば論理的に従動詞を2つの本動詞であるV1とV2に接続しなければなりません。
にもかかわらず、後者の動詞V2のみに接続するというほとんどの答案は等位接続詞andの根本的な構造的機能が理解されていないことを意味するのです。
この課題文の場合は、上記の解説で述べたように、as節の接続詞asは前節と後節両者の「動詞相互の関係」から、前節の「間接的な理由・原因(直接的な理由・原因の等位接続詞becauseの用法に類似している)」を表す「等位接続詞」ということになるのです。
もっとも、as節が文頭に来れば接続詞asの構造的機能は「従属接続詞」になるのですが(それはbecauseでも同様である)、同じ節であっても文頭にあるか文末にあるかの語順という位置関係によってセンテンス内での「効力関係」は異なってくるのです(この点について、前置用法の日本語は問題にならないが、後置用法の英語はデリケートな問題を生じる)。
ということは、その訳出は前節のV1 and V2を訳出した後、「というのは、~従動詞だから~」ということになるのです。
この分析法は、カンマ記号の構造的機能からの判断ではなく、「左から右へ」表現する英文構造における処理法は、言うまでもなく「左から右へ」処理しなければならないことによるものです。従って、等位接続詞andの構造的機能を処理した後に、後方のカンマ記号の構造的機能を処理するという手順になるのです。